ノリで「BASEMENT-TIMES」風に書いてみました。ちょっと毒が足りないけど。
=========================

いわゆる軽音部系クラブの顧問が口を揃えて言うのが、「イマドキの高校生はLIVEの楽しみ方が一様で気持ち悪い」と言う。LIVEを演る側ではなく、見る側・聴く側の話である。
何が気持ち悪いって、サビになると、あんまりやる気なさそうに、片手上げて、指を揃えた手のひらを演奏者側に向けて、やる気なさそうにリズムに合わせて動かす、あれである。そのやる気なさそうな感じたるや、下手をしたらTwitterのタイムラインを右手で辿りながら左手を挙げかねないレベルだ。ついでに言うと、ギターソロになると、腰をかがめてソリストに向かって両手をヒラヒラさせて「いまこの人がソロを弾いているんでござーい!」と分かりやすく示してあげる、あれもである。高校軽音になると、その挙句に演奏者がまともにソロが弾けてなかったりする。でも、やってあげるのだ、ヒラヒラを。ちゃんと練習して、弾けるようになってからステージに立てや。
高校生に、「ねえ。あのLIVEの時に、ああいう風に動いて、なんか楽しいことあんの?」と聞くと、苦笑いをする。「いやー。(あれが楽しそうに見えるなんて、どこに目がついてんですか?)。でも、どうすんですか?突っ立ってんですか?」とのこと。だいぶ脚色したけど。
じゃあなんでやるのさ、好きに楽しめばいいじゃん――ということを、常日頃からボンヤリと思っていた。先日参加した「高校生のバンドフェス」でも、「手なんて挙げなくていいからさ!好きに楽しんでよ!」なんていうMCを耳にした。どうだろう、高校生は本当に「好きに楽しむ」なんてマネが出来ていただろうか。
そう、その「フェス」である。CDなどという旧時代の遺物が売れなくなり、今やその媒体はカラスを追い払うくらいの価値しかない。音楽業界はビジネスモデルの転換を迫られ、もはやLIVEに足を運んでもらって、物販コーナーでタオルをたくさん買ってもらうしかない。
そして行き着くところはフェスだ。
いくつかの会場をまたにかけて、「この時間帯は〇〇ステージで××を見て、次に▲▲ステージに移って◎◎をみて…」という計画は、楽しそうだ。一日で上原ひろみからBABYMETALまで楽しめるなんて最高!
でもさ、みんなそんなに色んなアーティストの「予習」は出来てんの?フェスだったら、そのバンドの売れてる曲しかやらんのかもしれないけど、ひょっとしたらへそ曲がりなバンドがアルバムの3曲めあたりに配した曲を、しれっと演奏するかもしれないじゃない。
――などとボンヤリと考えていて、行きついた。「そっか、奴ら(=若い客)、予習なんか、たいしてしてないんだ!」 おそらくアニメとかCMなんかでタイアップした曲をYouTubeで何度か聞いて、それでもって「邦ロック最高」とか言ってウットリしていやがる。しかもYouTubeに繋ぐのはWi-Fi環境下のみだ。
おじさんが若い頃はなあ、「ふぇす」なんてもんはほとんどなくて、LIVEといったら大好きなアーティストとの2~3時間のタイマン勝負だ。たいがいは新譜を中心に演奏されるものの、アルバムを10枚~15枚出しているような大御所ともなると、うかつには参戦できない。そんなニワカ者には参戦の資格がない。だいたいヘビーメタルだハードロックだっちゅう音楽に限ると、スタジアムクラスの会場では残響が大き過ぎて、音の粒だとか刻みだとかはちゃんと聞こえない。どの曲のどのあたりではどういうリフが鳴っているのかをあらかじめ把握して、それをLIVE中に脳内補完しながら「うぉーメタルゴッド最高だぜ!」と楽しむものだ。「この曲、このLIVEで初めて聞いた」なんてことは、極力避けなければならない。逆に、「おいおい、こんな曲ミニアルバムにしか収録してないじゃんかよ(でもちゃんと知ってるぜぇ、予習済みですぜぇ)。」とニヤニヤ楽しんだりするのだ。
お気づきのように、その姿は「オタク」文化と親和性が高い。BABYMETALが売れたのも、上記のようにタイマンのライブを楽しんできたメタルおじさんと、「好きなものは隅から隅まで完璧に把握する」アイドルオタクという、姿勢を共にする同志に受けたからに他ならない。
さて、もう答えは言うまでもない。今や音楽とは発表曲を隅から隅までを味わい尽くす類のものではなく、傾向としては「YouTubeのつまみ食い」、下手をしたら「LIVEでの一期一会」のものとなっている。
演奏する側は、客がなるべく知っていそうな自分たちの「売れた」曲を演奏しなくてはならない。のみならず、曲を知らないであろう客さえも、楽しんでもらうような「演出」なり「楽曲の分かりやすさ」なりを工夫しなければならない。
客の側は、アーティスト側から「こうやって楽しんでね」という指示(めいたもの)があれば、それに従うし、それがなければ一様に手を挙げていればいいのだ。そうすれば、「自分は今LIVEを楽しんでいる!オレ、生きてる!」という自己暗示が成立する。音源を聞きこむ予習なんていらない。
翻って、高校軽音。首都圏近郊では、各学校を会場として複数の高校軽音部が集まる「合同ライブ」が行われ、ライブハウスやレコード会社、専門学校などが主催するコンテストイベントにも多く「部活バンド」が参加する。一握りの実力あるバンドは、音源を公開したり、さまざまなライブやコンテストを荒らし、皆に曲を知ってもらえているが、そんなバンドはごくごく一握り。だいたいはLIVEでの「一期一会」である。
でも、せっかく見に行ったからには楽しく見たい(聞きたい)し、演奏する側にしてみても楽しんでもらいたい。そうした一期一会の関係の中での、暗黙の了解が、あの「動き」なのである。目の前で繰り広げられている音楽が素敵なら、もちろん楽しく聞くだろうし、そうでなくても、「つまみ食い&一期一会」音楽文化にあっては、その曲を聞きこんでいようがいまいが(知っていようが知っていまいが)、「音楽とLIVEを愛するワタシ」はLIVEで手を挙げることによって、この音楽シーンに参入しているという調和が成立する。
分かったよ。そういうことなら、もう「気持ち悪い」なんて言わないよ。好きにおやり。

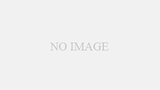
コメント